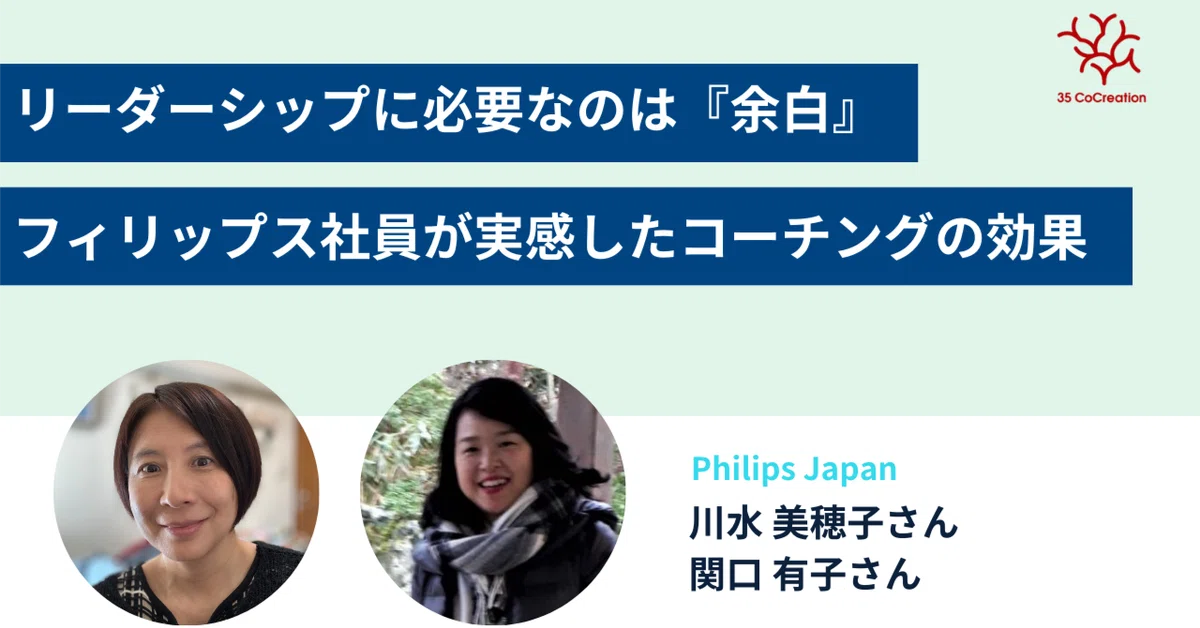コーチングを通して次世代リーダー育成を支援する、35 CoCreation(サンゴ コ・クリエーション)CEOの桜庭です。
今回は、次世代リーダーシップ養成スクール「Leader as Coach®」(以下、「Leader as Coach®」)に参加していただいた、株式会社フィリップス・ジャパン様の体験談をお届けします。
革新的な技術で人々の健康と豊かな生活を追求する同社は、コーチングを組織に取り入れ、リーダーの成長を力強く後押ししています。
シニアステージを前に、自身のリーダーシップをさらに磨きたいと考えていたという、Legal Compliance Department(リーガルコンプライアンス部門)のCompliance Officerである関口有子さん。上司の勧めで当社の次世代型リーダー養成スクールを受講した彼女は、オントロジカル・コーチングによる「体を使う」学びを通して、自身の言動のクセに気づき、人との関わり方における重要な変化を実感したといいます。
本記事では、関口さんの上司であるLegal International MarketsのHead of Legal Compliance/GBP Compliance Officer である川水美穂子さんに、コーチングがもたらした具体的な効果や、組織への影響についてお話を伺いました。
「可能性をさらに広げたい。それが受講のきっかけでした」
ーまず、関口さんに「Leader as Coach®」を受講してもらうように勧めたのは、どんなきっかけがあったのでしょうか。
川水さん:
関口さんは、より上位のポジションへの昇進を目前に控え、長年培ってきた専門性を究める道とマネジメントの道、どちらを主軸に成長を描くべきかという一つの岐路に立っていました。
私は、リーダーシップとは役職に紐づくものではなく、プロジェクトマネジメントや部署間の連携など、人と協働するあらゆる場面で発揮されるべきものだと考えています。彼女には、今回のコーチングを通じて自分の可能性をさらに広げ、どちらの道を選んだとしても自信を持ってリーダーシップを発揮できるようになってほしいと願い、受講を勧めました。

ー関口さん自身はLeader as Coach®を受けることについて、当初どのように思われていたのでしょうか?
関口さん:
コーチングという言葉は知っていましたが、具体的に何をするのか、正直なところイメージが掴めていませんでした。ただ、川水さんから提案を受けた際、自分自身もリーダーシップなど、更なる成長をしたいという課題感を持っていたので、迷わず受講を決めました。
私は仕事に対して、常に情熱を持って取り組んできたつもりです。しかし、結果を出すことやプロジェクトを完遂することに意識が集中しすぎてしまい、人を見る視点が不足していると感じていました。より上位のポジションに進むにあたり、もっと人を重視した関わり方が必要だと感じていたんです。
以前の職場では、複数の部下を持つ経験もありましたが、それぞれの個性に合わせた関わり方に苦労した記憶があります。現在は部下が一人ですが、これからシニアステージに進むと、より多くのメンバーと仕事をする機会も増えます。だからこそ、今回の「Leader as Coach®」を通じて自分自身の軸を確立し、相手を尊重しながらも状況に左右されない安定したリーダーシップを発揮できるようになりたいと思ったのです。

身体が知っている、本当の自分
ー関口さんは実際に受講されてみて、どんな発見がありましたか?
関口さん:
オントロジカル・コーチングでは、「身体を使う」という方法を取り入れますが、これがいつもの座学研修とは全然違って、本当に驚きの連続でした。感情と身体の動きが繋がっていることに気づき、身体を使うことで自分のことを深く理解できたんです。
例えば、演劇みたいに身体を動かすワークショップでは、普段は言葉やロジックに頼った表現になりがちだった自分のクセを、客観的に見ることができました。まるで、もう一人の自分が上から見ているような「ビッグアイ(観察眼)」という視点を学び、自分の状態に気づくポイントが増えたことで、「どんな自分でいるか」をいつも意識することの大切さを実感しました。
そんな中で、自分にはこんなクセがあるんだと気づいたことがあります。それは、人に何か伝えようとする時、気持ちが焦って、身体が無意識に前のめりになってしまうことです。知らず知らずのうちに相手にプレッシャーを与えているかもしれない、と気づけたことで、状況に合わせて一歩引いてみたり、瞑想で心を落ち着かせたり、深く呼吸をしてみたりと、いろいろな対処法を試しています。
そうやって普段から自分の言動を意識してみると、仕事が忙しい時や体調が悪い時、プレッシャーを感じる時に「タスクモード」になりやすいことにも気づきました。そうすると、どうしても部下やメンバーに「こうあらねばならない」と押し付けてしまうことにもなりかねません。まずはそんな自分の状態に気がつくことを意識できるように、今もトレーニングを続けています。
「自分の在り様」が「組織の在り様」を変えていく
ー「Leader as Coach®」のセッションを通して、どんなことが学びになりましたか?
関口さん:
リーダーとして成長するためには、部下の成長を促すための「余白」を作ることが大切だと気づきました。そして、「どんな自分でいるか(being)」という在り方が安定していることが重要で、それによって部下の方と良い距離感や関係性を築くことができると学びましたね。
思えば、コンプライアンス部ということもあって、これまでは相手がどんな状況なのかをちゃんと見ずに、ついあれこれと口に出してしまうことがよくありました。しかし、目に見えていることや結果の裏には、どんな思いや行動があるのか。そこにも意識を向けることが大切で、そういう姿勢で部下や周りのメンバーと向き合うことでこそ、信頼関係が生まれていくのだと思えるようになりました。
これからは少し気持ちに余裕を持って、「相手をよく観察する」「相手が何を求めているのかをしっかり聞く」「相手の反応を見ながら必要なことだけを伝えて、あとは相手に質問してもらう時間を作る」など、いろいろなアプローチができるように、自分の幅を広げていきたいと思っています。いい距離感を保ちながら、部下や周囲の成長をサポートしていけるような関係を築いていきたいです。
川水さん:
関口さんのフィードバックから、彼女は本当に良い影響を受けているなと感じています。
もし仕事をする上で、結果だけを求めるのであれば、組織に人がいる必要はなくなってしまいます。今は、情報は検索すればすぐに出てきますし、文章はAIが作ってくれますし、「作業」をしてくれる人はいくらでも外部に委託できます。そんな中で、組織の中に人がいる理由って何だろうと考えたときに、やはり、複数の人が関わり合うプロセスが非常に大事で、そこにこそより大きな価値があると思うんです。
例えば、お互いに信頼関係があるからこそよりスムーズに物事が進むとか、より良いものが生み出されるとか。それは、すぐには大きな成果に繋がるものではないかもしれません。
ただ、リーダーがそれを認識して動いているのか、あるいはただ結果だけを求めているのかというのはすごく大事で、そこにいるメンバーの意識やモチベーションにも大きく影響していくと思っています。広い視野を持ち、プロセスを大切にする人は、同じ考えを持つ人を惹きつけ、一緒に成長できる組織を作ることができます。
長い目で見たときに、一人ひとりの在り方が組織全体へと広がっていくと思っていますし、そんな効果を期待しています。
ーありがとうございました!
会社概要
■株式会社フィリップス・ジャパン
株式会社フィリップス・ジャパンは、ロイヤル フィリップスの日本法人として1953年に創業以来、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指しています。主な事業領域は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、睡眠・呼吸治療、およびパーソナルヘルスと多岐に渡ります。ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーとして、超高齢化が進む日本の医療・健康課題解決に向け取り組んでいます。日本の従業員数は約2,000人、約70拠点でビジネスを展開しています。
HP:https://www.philips.co.jp/